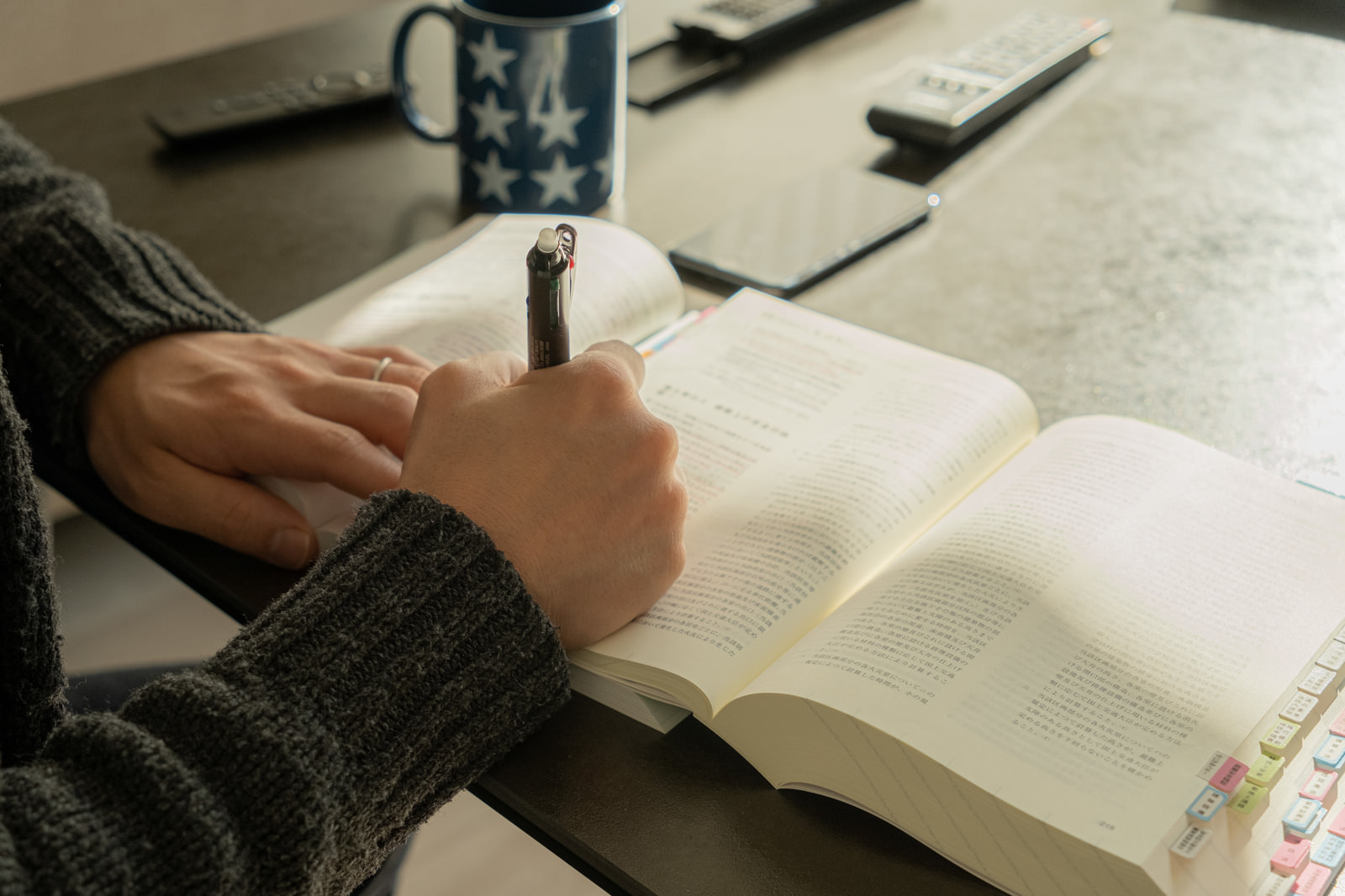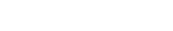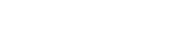社会人になってから、昔より、覚えられなくなってきている、、気がして、効果的な学習方法を科学的な根拠に基づいて紹介する本を読んでみました。
最初にまず科学的に効果が高くない勉強法が紹介されます。教科書や本は何度も繰り返し読んだ方が良いとどこかで聞いたり、読んだりしたことがあると思いますが、、
今までの自分のやり方が・・・非効率なものが多々ありショックをうけました。。
まず非効率な勉強法が紹介されます。
非効率的な勉強法
目次
繰り返し読むだけの学習
繰り返し読むだけの学習は長期的な記憶定着に効果が低い
単純な再読は「わかった気になる」だけで、深い情報処理が行われにくい
再読した学生と1回だけ読んだ学生の間で、ほとんどの場合に優位な差がなく、再読に大きな学習効果がないことを裏付ける結果となった。
2回目以降の読み込みでは、文章に慣れて「わかった気」になりやすく、深い情報処理が行われにくい。
ノートに単純に書き写す
教科書や参考書の内容をそのままノートに書き写す、まとめることは、学習効果が低い
アメリカの高校生を対象とした研究では、文章をそのまま書き写した生徒の成績は、ただ文章を読んだ学生と変わらなかった
マーカーを引くだけの学習
テキストにマーカーを引くだけでやった気がになってしまい効果的な学習にならない

・・・・・完全やった気になってます。
これらの勉強法に共通する問題点は、表面的な情報処理に留まり、深い理解や長期的な記憶定着につながりにくいことです。特に、「流暢性の錯覚」と呼ばれる現象により、実際には内容を十分に理解・記憶していないにもかかわらず、理解した気になってしまうリスクがあるようです。
効果的な勉強法
アクティブ・リコール
学習内容を単に復習するのではなく、意識的に思い出すプロセスを通じて記憶を定着させる学習法です。この方法は、科学的に証明された最も効果的な記憶法の一つとして広く認識されています。
学んだ内容を積極的に「思い出す」ことを中心に構成されています。
なるべく手がかりなしに記憶から引き出そうとする作業が重要
・練習問題、過去問を解く、模試をうける
・暗記カード、フラッシュカードを使う
・紙に書きだす
反復と間隔を空けた復習
短期間に詰め込むのではなく、時間を空けて復習する「間隔効果」を利用することで記憶が定着しやすくなる。
アウトプット重視の学習
インプット(読む)から アウトプット(思い出す、教える)に重点を置き学んでいく
モチベーション維持の方法
学習内容と自分との関連性を考え、紙に書き出す
自分に関連した情報の方が記憶に残りやすく、モチベーションも維持しやすい
本を読んでみて
効率的な学習法を科学的な視点から解説しています。この本では、実際の学習理論や心理学的な研究を元に、より効果的に勉強を進めるための方法、事例が詳しく紹介されてました。
自分自身にも試す価値のあるものが多かったです。取り組んで見ようと思いました。